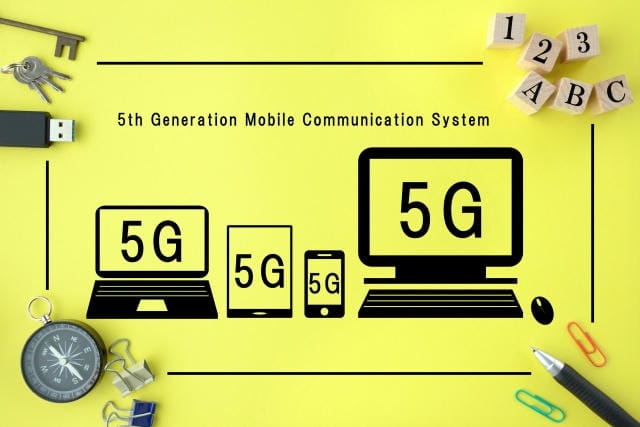情報通信技術の進展とともに、企業や組織の業務環境は著しく変化している。働き方の多様化による社外からのシステムアクセスが一般化し、様々なデバイスがビジネスインフラに加わった。こうした状況下、業務用端末、スマートフォン、タブレットといった各種機器が外部からの攻撃の入り口となりやすくなっている。これら端末それぞれへの防御が情報資産の保護において極めて重要となるため、各組織は網羅的な対策を講じる必要がある。サイバー攻撃は年々複雑化し、標的型や多層的な手法が当たり前になっている。
従来型の単純なウイルスやワームによる侵害だけではなく、使用者に成りすましてネットワークに侵入し、機密情報を窃取または改ざんするなど、様々な不正による手法が取られている。攻撃者が最初に狙うのが、利用者が日常的に操作する端末だということも多く、組織としては使用する端末ごとに多層的なセキュリティレイヤーを構築して、あらゆる不正な侵害を未然に防ぐ必要が生じている。情報流出やシステム破壊など大きな被害をもたらすサイバー攻撃の多くは、端末を踏み台にして社内ネットワークへ侵入することから始まる。これは、端末が直接外部インターネットと接続しているため、標的となることが容易だからだ。メールの添付ファイルやソフトウェアの脆弱性を利用する攻撃、外部メディア経由のマルウェア感染など、侵入経路は多岐にわたり、攻撃者はこうした多様な隙きを突く。
また、一度攻撃が成功すると管理者権限を奪い取って社内ネットワーク全体に不正な活動を広げていくため、端末一台の防御だけでなく、端末間の通信の監視や制御も対策に含める必要がある。従来用いられてきたセキュリティ対策としては、ウイルス対策ソフトにより既知のマルウェアの検出と駆除を行う方式が主流だった。しかし、これだけではサイバー攻撃の高度化・多様化についていけなくなっている。未知のマルウェアやゼロデイ攻撃、新たな不正手法に対しては、従来型の対策では十分な防御効果が期待できない。このため、端末ごとに行動ベースで不審な動きを検知したり、アプリケーションの通信を精査して異常アクセスを遮断したりするような新しい技術を導入する動きが広まっている。
防御と検知、さらには即時対応まで含めた多層的な対策が、組織の情報資産を守るうえで欠かせないものとなっている。また、悪意のある外部攻撃者だけでなく、内部者による不正も大きなリスクをもたらす。組織内の利用者が何らかの原因で業務端末を不正利用した場合、意図せず情報漏えいに加担するケースも考えられる。従業員や取引先が端末に不審なファイルを持ち込む場合や、Webサイト経由で偽装アプリケーションを誤ってインストールする場合など、内部からのリスクも把握しなければならない。そのため、端末へのアクセス権を厳密に管理し、アクセスログを定期的に監査するとともに、不正な操作を自動で検知し、必要に応じてアカウントの一時停止や隔離など迅速に対応する仕組みが有効とされる。
加えて、リモートワークやクラウドサービスの利用拡大により、従来のような物理的な境界防御だけでは十分なセキュリティを確保することが難しくなっている。端末の所在地を問わず一律に防御が必要な状況となり、端末自体の管理体制を強化する必要性が高まっている。端末の利用状況や状態を常時監視し、最新のアップデートを自動適用する仕組み、利用アプリの制御など、運用管理面も含めた総合的な対策が要求されている。このような背景から、端末における適切なセキュリティ対策を組み合わせることで、組織全体としての安全性を高める取り組みが続いている。その例としては、端末単体の挙動監視とネットワーク通信監視を同時に行い、不審なアクセスや外部への情報送信を早期に発見するものや、端末に保存されているデータの暗号化、メディア接続の管理などが挙げられる。
あわせて、利用者へのセキュリティ教育も重要で、従業員一人ひとりに危険な挙動を理解させ、不審なメールやファイルへの注意喚起を行うことも対策の一部である。エンドポイントを標的とするサイバー攻撃や不正な行為がもたらす被害の深刻さは年々高まっている。被害を未然に防ぎ、情報資産を守るためには、多様化する攻撃手法への理解とともに、技術・運用・人の管理が一体となった総合的なセキュリティ態勢の強化が欠かせない。現状に甘んじることなく、絶えず防御態勢の見直しと最新のテクノロジーの導入による不断の対応が重要と言える。情報通信技術の進歩により、企業や組織の業務環境は大きく変化し、多様な端末からシステムへアクセスすることが一般的となった。
しかし、この変化はサイバー攻撃の新たな入り口を増やし、端末ごとの防御がかつてなく重要になっている。攻撃者は端末を踏み台にして社内ネットワークへ侵入し、機密情報の窃取やシステム破壊を狙う。不正アクセス手法も巧妙化し、従来のウイルス対策ソフトだけでは十分に対応できないため、端末の挙動監視やネットワーク通信の制御、データ暗号化など多層的な対策が必要不可欠となる。また、外部からの攻撃だけでなく内部不正やヒューマンエラーによるリスクも増大しているため、アクセス権限の厳格な管理、操作ログの監査、不審な動きに即応できる運用体制が求められる。加えて、リモートワークやクラウドサービスの拡大により、物理的な境界防御だけに頼らず、端末自体の管理や常時監視が不可欠である。
情報資産の保護には、技術的対策に加え、利用者へのセキュリティ教育も重視し、最新の攻撃手法に対応する不断の防御態勢の構築が不可欠である。